1.はじめに
急に思い立って香港に行ってきました。
香港は初めての訪問です。製品の開発・生産が経済の原点である、と考えて
いる者としては、流通などのサービス業が中心であろう香港には興味があり
ませんでした。しかし、自分の好みでない社会を見学することも面白いかも
しれない、と考え直しました。
夜着朝発の3泊4日、1日ツアー観光+1日自由観光の慌ただしい日程で、
ちょっとだけ香港の雰囲気を感じてきました。

空港からホテルま
では約50キロ、車
で30分余りでした。
訪ねた場所は
バス観光の②~④
自由行動の⑤、⑥
です。
2.林立
まずは、高層マンションの林立している風景に圧倒されました。
.jpg) ←九龍地区の住宅地
↓ホテルの部屋(17階)から
←九龍地区の住宅地
↓ホテルの部屋(17階)から
.jpg)
香港の人口密度は、シンガポールに次ぎ、世界第2位だそうです。
しかし、香港は平地面積が少ないため、人口約700万人のうち半分以上が
住む住宅密集地域の人口密度は、世界のトップだろうと思います。
.jpg) ←空港近くのマンション(億ション?)
↓空港から九龍半島への途中
←空港近くのマンション(億ション?)
↓空港から九龍半島への途中
.jpg) 3.交通
3.交通
香港島には、開業してから100年以上も経つ路面電車が走っています。
この電車は狭い車体幅で2階建てなのが、いかにも香港トラムと呼ばれるの
に相応しい姿です。路線バスも2階建てです。
.jpg) ←トラム(香港島のセントラルにて)
↓路線バス(九龍半島にて)
←トラム(香港島のセントラルにて)
↓路線バス(九龍半島にて)
.jpg)
地下鉄も整備されています。
宿泊した九龍半島のホテルから香港島へは地下鉄を使いました。地下鉄の駅
のエスカレータは、日本よりもスピードが速いと感じました。車内の椅子が
アルミ製だったので、身体がこわばりました。
地下鉄の券売機が日本と変わっていました。
私が知っている限り、日本では目的地までの料金を表示パネルなどで確認し、
その料金に見合うボタンを押して券を買います。香港では、路線図上の各駅
にボタンが配置してあり、目的駅のボタンを押すと料金が表示されるように
なっていました。
.jpg) ←地下鉄構内の券売機
↓券売機の画面
←地下鉄構内の券売機
↓券売機の画面
.jpg)
空港と市内は高速道路で結ばれていてアクセスは良好です。
現在の空港は香港返還の翌年、1998年に開港されました。顧客満足度で
シンガポールと1位争いをしているようです。
旧空港(啓徳空港)の跡地はまだ空地のままでした。
.jpg) ←トラムを描いた絵の看板
(スタンレイにて)
↓旧空港跡地
←トラムを描いた絵の看板
(スタンレイにて)
↓旧空港跡地
.jpg) 4.慕情
4.慕情
香港で何を見物しようか、最初に思いついたのが百万ドルの夜景でした。
昔見たアメリカ映画の「慕情」が、ストーリーはほとんど忘れていますが、
音楽が頭の中に残っています。
香港島のビクトリアピークという山の頂上まで登山電車が走っています。
私は午前中にバスで行ったのですが、濃い霧で対岸はおろか、眼下の街もよ
く見えませんでした。
.jpg) ←山頂からの眺め
↓映画に登場したカフェ
←山頂からの眺め
↓映画に登場したカフェ
.jpg)
翌日の夜は好天に恵まれ、下の写真のような夜景を堪能しました。
これで旅行代は十分回収できました!
(ウソ、ウソ..山頂のピーク・タワーに掲示されていた写真です(涙..)
.jpg) 5.信心
5.信心
人口が密集しているのは香港島の北部と対岸の九龍半島です。
香港島南部のレパルスベイ(浅水湾)やスタンレイ(赤柱)と呼ばれている
地区は、リゾート地として賑わっているようです。
レパルスベイの天后廟では神様に頭を下げる人が多くいました。しかし、
ここはほとんどが観光客でしょうから、香港人が信心深いかどうかは判定で
きません。
.jpg) ←レパルス・ベイにて
↓
←レパルス・ベイにて
↓
.jpg)
香港で一番大きなお寺は、九龍半島の黄大仙廟のようです。
ここも一般の観光客が沢山訪れていました。しかし、線香に火をつけて祈る
人たちは、どうも香港に住んでいる人が多いのではないかという感じがしま
した。
.jpg) ←黄大仙廟にて
↓
←黄大仙廟にて
↓
.jpg)
参拝を終わっての帰り、駐車場出入り口脇の看板が眼に入りました。
どうやら中国共産党離党者の集計値を表示しているようです。ホワイトボー
ドに毎日数字を書き換えている様子でした。
.jpg)
.jpg) ↑駐車場出入り口 ↑看板の一部
6.金融
↑駐車場出入り口 ↑看板の一部
6.金融
香港はニューヨーク、ロンドンに並ぶ金融の街です。
その中心がセントラル(中環)で、HSBC(香港上海銀行)がその中核に
あると言ってよいでしょう。HSBCの設立は1865年、通貨発行の中心
的役割を果たしてきました。
HSBC香港本店前のスタチュースクエアに、一体の銅像が立っています。
初期の香港上海銀行頭取として活躍したトーマス・ジャクソン・バートだそ
うです。この広場はあまり広くはありませんが、きれいに掃除されていまし
た。土日には、フィリピンから出稼ぎにきている沢山の女性が息抜きに集ま
ってくるそうです。
.jpg) ←聳え立つHSBCビル
↓広場を象徴する銅像
←聳え立つHSBCビル
↓広場を象徴する銅像
.jpg)
銀行に用事のある人はエスカレータで2階に上がります。
ゆったりとしたスペース、行員のソフトな応対、フリードリンクのサービス
など、日本の銀行とは印象が違いました。富裕層は3階に案内されるそうで
す。
.jpg) ←HSBCへのエレベータ
↓こじんまりしたテント村?
←HSBCへのエレベータ
↓こじんまりしたテント村?
.jpg)
地上階の端に沢山のテントが張られているのに気づきました。
商品販売用にしてはやや不揃いだと思って警備員に聞いてみたところ、ここ
で生活している人がいるのだそうです。マンハッタンのウオール街で格差是
正を叫ぶ人がいますが、同様な人がここにもいるのかも知れません。
7.発砲
英国はアヘン戦争を仕掛けて清朝から香港島を割譲させました(1842
年)。植民地を統括する拠点は現在のセントラル(中環)でしたが、香港経
済を牛耳ることになるジャ-ディン・マセソン社は、セントラルの東方のコ
ーズウエー(銅鐸湾)に営業拠点を構えたそうです。
地下鉄でセントラルから東へ3つ目の銅鐸湾駅に行きました。
海岸で毎日正午に大砲が発射(空砲)される風景を見学するためです。この
行事はヌーンディガンと呼ばれ、1850年から続いているそうです。
.jpg) ←そごう百貨店のある銅鐸湾駅付近
↓ヌーンディガンの場所
←そごう百貨店のある銅鐸湾駅付近
↓ヌーンディガンの場所
.jpg)
ヌーンディガンは、ジャ-ディン・マセソン社が自衛のために砲台を構え
たことに始まり、現在も同社の職員が毎日発射しているのだそうです。
残念ながら定刻に間に合わなかったため、発射現場を見学することができ
ませんでした。
.jpg) ←発射場
↓近くのヨットハーバー
←発射場
↓近くのヨットハーバー
.jpg)
高層ビルが立ち並んでいる香港島北部と、その対岸にある九龍半島南部は
英国の植民地化後に大幅に埋め立てられたそうです。ヌーンディガンが据え
られた付近にあった銅鐸湾は全面的に埋め立てられました。なぜ銅鐸の語が
使われているのか、ガイドさんに聞いてみましたが分かりませんでした。
8.懸念
ホテルの近くに牛丼の吉野家がありました。
地下鉄ヤウマテイ(油麻地)駅の近く、九龍半島を南北に走るネイザンロー
ド(彌敦道)に面していました。
.jpg)
夕方だったこともあり、次々にお客
さんが入っていました。香港では外食
する人が多く、3食とも外食の人が結
構いるそうです。
この店でキャンペーンを張っていた
のは「しゃぶしゃぶ」でした。(60
HKD位?だったか)
←吉野家
試しに牛丼を食べてみ ました。
並み牛丼+味噌汁かコーラで31HKD(約¥400)でした。日本での実
態を知っている者としては少し割高感があります。ちなみに、私は吉野家に
は行きませんが、我が家近くの「すき屋」では、並みの牛丼+味噌汁+サラ
ダで¥390です。
客の満足度は付帯サービスにも依存するでしょう。
日本のすき屋では、無料サービスとして、刻みショーガ、水、紙ナプキン、
楊枝、七味がついています。この店ではただ牛丼を提供するだけです。
私が愕然としたのはタバコです。
香港への煙草の持ち込みは19本まで、20本以上からは税金がかかるのだ
そうです(2010年8月から)。関空を発つときはいつも免税店で買い込
んでいくのですが、今回は断念しました。
.jpg)
香港では喫煙できないのか?
これはあまり気にするまでもありません
でした。
たしかに、建物内では原則禁煙となっ
ているようです。しかし、道路脇にはあ
ちこちに灰皿が配置されていました。
←道路脇の灰皿(銅鐸湾駅付近)
ちょっと見渡せば、色は違っても同じ形状の灰皿が眼につきます。
つまりは、香港には喫煙者が多いのでしょう。医療保険制度がどうなってい
るのかは知りませんが、医療費を政府が負担しないのであれば、タバコの持
ち込み制限は、要するに香港での売り上げを伸ばすための政策なのでしょう。
なお、香港国際空港の免税店では、マイルドセブン1カートンが(記憶が
あいまいですが)135HKD(約¥1,800)でした。
9.おわりに
日本ではようやく寒波が収まる時期でしたが、香港は春みたいだろう、と
考えていたのが誤りでした。確かに気温は日本よりも高かったのですが、ホ
テルの部屋が寒くてすぐに香港風邪!をひきました。湿度が高い香港では年
中全館冷房しているとのこと。(情報の確度は分かりません)
ホテルから空港への帰路、元日本人のガイドさんが添乗しました。
香港で40年以上暮らしているという70歳台のお姉さんでした。香港では
年金制度がないそうです。お姉さんは動ける間は働き続けるのかも知れませ
ん。
中国に返還された後の香港はどうあるべきと香港人は感じているのか?
香港で生活している人から直接聞く機会はありませんでしたが、ガイドさん
の話しぶりや人々の雰囲気などからの印象として、香港はこのままであるこ
とを望んでいるようです。もっとも、この稿を書き終えるつい先ほど、香港
長官に親中派財界人の梁氏が当選したとのニュースがありました。(今回ま
では間接選挙でしたが、次回からは直接選挙になるそうです)
(散策:2012年3月14日~3月17日)
(脱稿:2012年3月25日)
-----------------------------------------------------------------
この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ
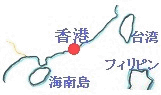
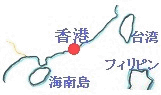
空港からホテルま では約50キロ、車 で30分余りでした。 訪ねた場所は バス観光の②~④ 自由行動の⑤、⑥ です。 2.林立 まずは、高層マンションの林立している風景に圧倒されました。
←九龍地区の住宅地 ↓ホテルの部屋(17階)から
香港の人口密度は、シンガポールに次ぎ、世界第2位だそうです。 しかし、香港は平地面積が少ないため、人口約700万人のうち半分以上が 住む住宅密集地域の人口密度は、世界のトップだろうと思います。
←空港近くのマンション(億ション?) ↓空港から九龍半島への途中
3.交通 香港島には、開業してから100年以上も経つ路面電車が走っています。 この電車は狭い車体幅で2階建てなのが、いかにも香港トラムと呼ばれるの に相応しい姿です。路線バスも2階建てです。
←トラム(香港島のセントラルにて) ↓路線バス(九龍半島にて)
地下鉄も整備されています。 宿泊した九龍半島のホテルから香港島へは地下鉄を使いました。地下鉄の駅 のエスカレータは、日本よりもスピードが速いと感じました。車内の椅子が アルミ製だったので、身体がこわばりました。 地下鉄の券売機が日本と変わっていました。 私が知っている限り、日本では目的地までの料金を表示パネルなどで確認し、 その料金に見合うボタンを押して券を買います。香港では、路線図上の各駅 にボタンが配置してあり、目的駅のボタンを押すと料金が表示されるように なっていました。
←地下鉄構内の券売機 ↓券売機の画面
空港と市内は高速道路で結ばれていてアクセスは良好です。 現在の空港は香港返還の翌年、1998年に開港されました。顧客満足度で シンガポールと1位争いをしているようです。 旧空港(啓徳空港)の跡地はまだ空地のままでした。
←トラムを描いた絵の看板 (スタンレイにて) ↓旧空港跡地
4.慕情 香港で何を見物しようか、最初に思いついたのが百万ドルの夜景でした。 昔見たアメリカ映画の「慕情」が、ストーリーはほとんど忘れていますが、 音楽が頭の中に残っています。 香港島のビクトリアピークという山の頂上まで登山電車が走っています。 私は午前中にバスで行ったのですが、濃い霧で対岸はおろか、眼下の街もよ く見えませんでした。
←山頂からの眺め ↓映画に登場したカフェ
翌日の夜は好天に恵まれ、下の写真のような夜景を堪能しました。 これで旅行代は十分回収できました! (ウソ、ウソ..山頂のピーク・タワーに掲示されていた写真です(涙..)
5.信心 人口が密集しているのは香港島の北部と対岸の九龍半島です。 香港島南部のレパルスベイ(浅水湾)やスタンレイ(赤柱)と呼ばれている 地区は、リゾート地として賑わっているようです。 レパルスベイの天后廟では神様に頭を下げる人が多くいました。しかし、 ここはほとんどが観光客でしょうから、香港人が信心深いかどうかは判定で きません。
←レパルス・ベイにて ↓
香港で一番大きなお寺は、九龍半島の黄大仙廟のようです。 ここも一般の観光客が沢山訪れていました。しかし、線香に火をつけて祈る 人たちは、どうも香港に住んでいる人が多いのではないかという感じがしま した。
←黄大仙廟にて ↓
参拝を終わっての帰り、駐車場出入り口脇の看板が眼に入りました。 どうやら中国共産党離党者の集計値を表示しているようです。ホワイトボー ドに毎日数字を書き換えている様子でした。
.jpg)
↑駐車場出入り口 ↑看板の一部 6.金融 香港はニューヨーク、ロンドンに並ぶ金融の街です。 その中心がセントラル(中環)で、HSBC(香港上海銀行)がその中核に あると言ってよいでしょう。HSBCの設立は1865年、通貨発行の中心 的役割を果たしてきました。 HSBC香港本店前のスタチュースクエアに、一体の銅像が立っています。 初期の香港上海銀行頭取として活躍したトーマス・ジャクソン・バートだそ うです。この広場はあまり広くはありませんが、きれいに掃除されていまし た。土日には、フィリピンから出稼ぎにきている沢山の女性が息抜きに集ま ってくるそうです。
←聳え立つHSBCビル ↓広場を象徴する銅像
銀行に用事のある人はエスカレータで2階に上がります。 ゆったりとしたスペース、行員のソフトな応対、フリードリンクのサービス など、日本の銀行とは印象が違いました。富裕層は3階に案内されるそうで す。
←HSBCへのエレベータ ↓こじんまりしたテント村?
地上階の端に沢山のテントが張られているのに気づきました。 商品販売用にしてはやや不揃いだと思って警備員に聞いてみたところ、ここ で生活している人がいるのだそうです。マンハッタンのウオール街で格差是 正を叫ぶ人がいますが、同様な人がここにもいるのかも知れません。 7.発砲 英国はアヘン戦争を仕掛けて清朝から香港島を割譲させました(1842 年)。植民地を統括する拠点は現在のセントラル(中環)でしたが、香港経 済を牛耳ることになるジャ-ディン・マセソン社は、セントラルの東方のコ ーズウエー(銅鐸湾)に営業拠点を構えたそうです。 地下鉄でセントラルから東へ3つ目の銅鐸湾駅に行きました。 海岸で毎日正午に大砲が発射(空砲)される風景を見学するためです。この 行事はヌーンディガンと呼ばれ、1850年から続いているそうです。
←そごう百貨店のある銅鐸湾駅付近 ↓ヌーンディガンの場所
ヌーンディガンは、ジャ-ディン・マセソン社が自衛のために砲台を構え たことに始まり、現在も同社の職員が毎日発射しているのだそうです。 残念ながら定刻に間に合わなかったため、発射現場を見学することができ ませんでした。
←発射場 ↓近くのヨットハーバー
高層ビルが立ち並んでいる香港島北部と、その対岸にある九龍半島南部は 英国の植民地化後に大幅に埋め立てられたそうです。ヌーンディガンが据え られた付近にあった銅鐸湾は全面的に埋め立てられました。なぜ銅鐸の語が 使われているのか、ガイドさんに聞いてみましたが分かりませんでした。 8.懸念 ホテルの近くに牛丼の吉野家がありました。 地下鉄ヤウマテイ(油麻地)駅の近く、九龍半島を南北に走るネイザンロー ド(彌敦道)に面していました。
夕方だったこともあり、次々にお客 さんが入っていました。香港では外食 する人が多く、3食とも外食の人が結 構いるそうです。 この店でキャンペーンを張っていた のは「しゃぶしゃぶ」でした。(60 HKD位?だったか) ←吉野家 試しに牛丼を食べてみ ました。 並み牛丼+味噌汁かコーラで31HKD(約¥400)でした。日本での実 態を知っている者としては少し割高感があります。ちなみに、私は吉野家に は行きませんが、我が家近くの「すき屋」では、並みの牛丼+味噌汁+サラ ダで¥390です。 客の満足度は付帯サービスにも依存するでしょう。 日本のすき屋では、無料サービスとして、刻みショーガ、水、紙ナプキン、 楊枝、七味がついています。この店ではただ牛丼を提供するだけです。 私が愕然としたのはタバコです。 香港への煙草の持ち込みは19本まで、20本以上からは税金がかかるのだ そうです(2010年8月から)。関空を発つときはいつも免税店で買い込 んでいくのですが、今回は断念しました。
香港では喫煙できないのか? これはあまり気にするまでもありません でした。 たしかに、建物内では原則禁煙となっ ているようです。しかし、道路脇にはあ ちこちに灰皿が配置されていました。 ←道路脇の灰皿(銅鐸湾駅付近) ちょっと見渡せば、色は違っても同じ形状の灰皿が眼につきます。 つまりは、香港には喫煙者が多いのでしょう。医療保険制度がどうなってい るのかは知りませんが、医療費を政府が負担しないのであれば、タバコの持 ち込み制限は、要するに香港での売り上げを伸ばすための政策なのでしょう。 なお、香港国際空港の免税店では、マイルドセブン1カートンが(記憶が あいまいですが)135HKD(約¥1,800)でした。 9.おわりに 日本ではようやく寒波が収まる時期でしたが、香港は春みたいだろう、と 考えていたのが誤りでした。確かに気温は日本よりも高かったのですが、ホ テルの部屋が寒くてすぐに香港風邪!をひきました。湿度が高い香港では年 中全館冷房しているとのこと。(情報の確度は分かりません) ホテルから空港への帰路、元日本人のガイドさんが添乗しました。 香港で40年以上暮らしているという70歳台のお姉さんでした。香港では 年金制度がないそうです。お姉さんは動ける間は働き続けるのかも知れませ ん。 中国に返還された後の香港はどうあるべきと香港人は感じているのか? 香港で生活している人から直接聞く機会はありませんでしたが、ガイドさん の話しぶりや人々の雰囲気などからの印象として、香港はこのままであるこ とを望んでいるようです。もっとも、この稿を書き終えるつい先ほど、香港 長官に親中派財界人の梁氏が当選したとのニュースがありました。(今回ま では間接選挙でしたが、次回からは直接選挙になるそうです) (散策:2012年3月14日~3月17日) (脱稿:2012年3月25日) ----------------------------------------------------------------- この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ